パンクの時代
- 2012.01.22
- 日記
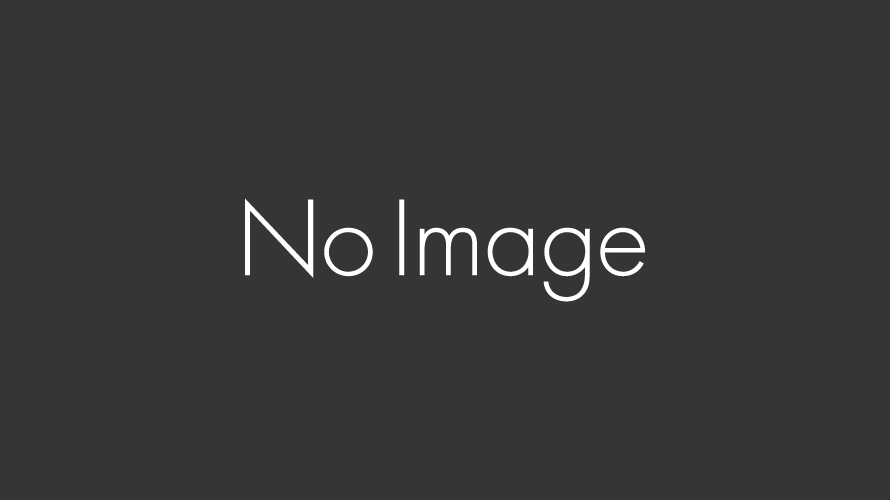
今、僕がルパンのような大仕事をしても証拠が残らないだろう。
自転車のパンク修理をしていて、瞬間接着剤で親指と中指がくっついて離れなくなり、それを無理矢理離したら指紋が無くなったのだ。何を触れても証拠残らず。
オチもついていて、パンクした箇所をふさいだ後、空気を力任せに入れてたら、チューブが破裂してしまった。
パンクと言えば、同じパンクでも車のパンク。
86年の渡米当時、僕はF1のチームに雇ってもらえそうなくらいパンクの交換が速かった。
最初に買った車が1000ドルのフォードで、2代目は500ドルのトヨタ。
車もボロボロだけど、タイヤも負けないくらいボロボロでしょっちゅうパンクしてた。
パンクしても新しいタイヤなんか買えないから、中古の表面がツルツルのタイヤを20ドルくらいで買ってきては間に合わせる。
20ドルのタイヤというのはある種ギャンブルで、余命1週間だったりする。
後ろのタイヤがパンクすると車がお尻を振ることがある。
振動するミラー越しに、蜘蛛の子を散らすように後続の車が僕の車を避けて奔る。
そんな時にも僕は割と冷静に、右側の方向指示器を出して車線変更をしながら路肩に車を移動させた。
思い出した。
パンクだけじゃなく、ガス欠も珍しくなかった。有り金10ドルとか20ドルしか入れられないから、すぐに無くなるうえ、いつもぼーっとしてるから残量をチェックするのを忘れるのだ。
こっちは路肩に寄せるのが、パンクよりもかなり難易度が高い。
突然怒ったようなプスンプスンという音がして車は失速。わずかな勢いが残っているうちに車線変更を迫られる。
関西では「必死のパッチ」と言うけど、その最上級の「必死のパッチ」だった。運転しててスプレーを吹くように涙が出るんだから。
右後方にトレーラーとかが迫ってたら涙は洪水だ。
そんなこともあったというより、そういうことが日常だった。
20歳代前半。あの頃も面白かったなあ。